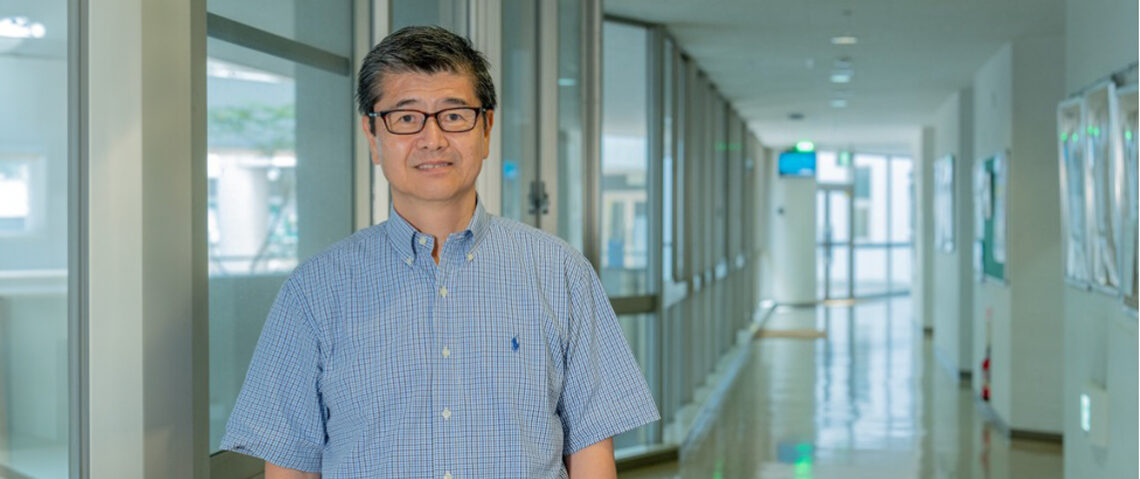――改めて、先生のプロフィールについて伺います。どのようにして本学に着任されたのですか?
2006年に着任しました。もうずいぶん経ちましたね。
もともとは10年ほど、アメリカで手話言語学の研究をしていました。その後アメリカで3年間教員をやって、帰国後は全日本ろうあ連盟の本部事務所長 となりました。手話言語学の教育・研究は終わりにして、これからはろうあ運動に邁進するぞと決めたんです。お名前を挙げきれないくらい、多くの素晴らしい先輩方にかわいがっていただきました。
同じ頃、長年ろう学校で教鞭を取られ、後に筑波技術短期大学(当時)に移られた根本匡文(ねもと まさふみ)先生という方がいらっしゃいました。きこえない学生が将来に向けて身に着けておくべき知識や心の持ちようなど、大切なことを教えておられました。その根本先生が訪ねて来られて、「頼む、本学に来てほしい」とおっしゃるんです。大変光栄なお話でしたが、既に自分の道はろうあ運動にあると一度はお断りしました。するとその翌年、そのまた翌年にもお見えになって、「短大から四年制大学になる、その変革期にあなたが必要だ」と熱心に説得されました。幾度もわざわざ足を運んで下さった、その熱意に根負けしてお話を受けることにしました。結果、前職の関係者からは白い目で見られましたが(笑)。
――本学着任後は、どのようなお仕事をされてきたのですか。
根本先生はきこえる方でしたが、「後継には当事者教員を。大杉をおいて他にない」と言って下さったんです。その後審査を経て正式に採用され、根本先生が担当なさっていた授業をそっくり私が引き継ぎました。
引き継いでみたら、科目名が全て「聴覚障害なになに」という名前でした。確かに内容的にはそうだろうとは思ったものの、一様に並ぶ「聴覚障害」の文字にどうにも違和感を覚えました。私自身は、自分は当事者かつ実務家教員だから、私に求められているのはそれまでの社会経験から得られたものを学生たちに還元していくこと、それが教育の面では大きいのだろうと考えていました。その考えのもとに、それぞれの科目の中身を少しずつ修正していきました。
その後、カリキュラム改編のタイミングで、科目名の変更を提案してみました。内容によって「聴覚障害」「きこえない」「ろう・難聴」と言葉を使い分けてみてはどうかと。それが通って、「聴覚障害」がいろいろな言葉で表されるようになり、よりカリキュラムに幅が出ました。それらの科目を総じて「ろう者学」と言います。当時の役職者の先生方からもろう者学を打ち出していくことに好意的なアドバイスをいただきました。そこから、「ろう者学」という言葉が表すものを映像や本などのいろいろなメディアでコンテンツ化していくプロジェクトも発足しました。
学生たちの卒業後には何が必要なのか考えてみると、やはりろう・難聴当事者にはろう者学の全てが必要なのだと思いました。周りの先生方からも少しずつ「技大にはろう者学がある。他の大学では学べない」という声をいただくようになって、とても心強い思いでした。ならば、「ろう者学が専門だ」と胸を張れるくらい充実した体系的なカリキュラムを作らなければ、と思ったのですが、そうすると今度は「ここはろう者学のための大学ではない」という声も上がりました(苦笑)。
どうしようかと思っていたら、別の視点での気づきがありました。本学でのキャリア教育は、かつては主に就職活動を見据えたものでした。ですが、そもそも「キャリア」という言葉は、人生におけるライフステージごとの様々な活動・行動のいずれもを指しています。その時々で、自分にできること・できないことを知り、本来の自分で周囲と関わり社会に参画していく。そうやって新しい自分を発見していく。他大学でも少しずつそのような考え方が見られますが、本学でも現在はその点を重視しています。
卒業後はきこえる人と一緒に働くことも、あるいはきこえない人たちだけで仕事をすることもあるでしょう。そういった様々な場面で仕事をしていくには、働くために必要な知識や技術以前にきこえない自分をどう表現するのかが肝要で、それはろう者学と通ずる考え方です。ならば、掲げる看板は何もろう者学でなくても良いと思いました。本学のキャリア教育の下支えにろう者学があるのならば、それで良いのだと。きこえない学生へのキャリア教育は、つまりイコールろう者学ではないかと。ずいぶん後になってそのことに気が付きました。
――着任当時から現在まで、先生の中での心境の変化のようなものはありましたか?
年は取りましたね(笑)。
的外れな答えかもしれませんが、今の学生たちは自分の子どもと同じくらいなんです。実際に子どもが二人いるんですが、ちょうど同じくらいの年代で。子どもたちにはいつも私の背中を見ろと言っています。大学でも、学生に同じことを言ってきました。そういう意味では、むしろずっとブレずにいますね。
――定年まであと3年半とのことですが、それについてはいかがですか?
現在「定活」中です。定年活動(笑)。
今は、自分が行なってきた教育・研究で使ったもの、培ったものを全部整理して、然るべきところに引き継ぐことに一番力を入れています。アメリカに行く前、18歳から28歳まで(1980年~1990年)はろう者の文化芸術活動を盛り立てる活動をしていたんですが、その当時、故米内山明宏さん(註:よないやま あきひろさん。1980年代のろう者演劇復興期における第一人者)との出会いが大きな転機となりました。知り合ってからの2年間は毎日のように米内山さんとのタンデムでいろんなところに行きました。私の手話はまるきり米内山さん仕込みです。その10年間で、全国津々浦々、多くのきこえない人たちのところを回りました。焼き物職人、竹細工職人、銭湯絵師、役者、いろいろな手仕事を生業にしている人たちに何人も会って資料にまとめる。そういう10年間でした。
それらの資料を長らく自宅で持て余していたんですが、定年を前に、研究室にある分と合わせて寄贈しようと思いました。本学でも、図書館の所蔵にない本やパンフレットなどの資料を受け入れてもらう準備を進めています。 その他のチラシや、米内山さんによる記述を含む私のノートや日記なんかは全て京都にある全国手話研修センターの資料室に寄贈することを決めています 。ただ、そのままでは渡された方も困るでしょうから、現在寄贈する資料をリストに起こしています。また、私が収集した手話の映像も、全てデータにしてアーカイブ化し、今後公開していく予定です。
残るは教育です。これを、次は誰に受け渡せばよいのか。それが今残された課題です。
――7月28日の本学主催イベント「ろう者学セミナー」で、「『大杉だからできるんだ』と言われてきたことを少しずつ周りの人に任せている」とおっしゃっていました。「大杉だからできる」という言葉には、どんな意味があったと思われますか?
私はあまり褒められた生き方はしていないですが(笑)、物事の善し悪し両面は知っているつもりです。一般的な会社勤めも、団体活動もしたことがある。研究活動もわかる。高校生の時は皿洗い、会計事務、魚屋などのアルバイトをやっていました。
という風に、それなりにいろいろ経験してきたので、若い世代のろう・難聴学生が揺れ動いたり必ずしも夢を持てずにいるのもわかります。そんな彼らにどんな種を渡せるか考えるのは、本職の方に失礼ですが薬の調合に似ています。それぞれの患者さんに合わせて調剤するように、この人にはどんなアドバイスが効くのか、どんな知識が必要か。その匙加減が割とうまくいっているのだと思います。その技術が今受け持っている授業の中にも活きていて、これは私にとっての手仕事と言っても良いと思います。18歳からの10年間で多くのきこえない人たちに会って、ほとんどが鬼籍に入られましたが、その方々の手仕事を幾度も目の当たりにしました。手仕事を見せていただく中で蓄積したその人たちの生き様を、今度は私の手仕事として(アドバイスの形で)学生たちに伝えていっているわけですね。
――普段、学生と接する時どんなことを心がけていらっしゃいますか。
まずは、相手の話を聞くようにしています。その学生にはどんなストーリーがあるのか、まず聞く。
今日(インタビュー日)の午前中、卒業生夫妻にインタビューをしたんです。今は私がされている方ですね(笑)。2人ともバドミントンの選手なのですが、旦那さんの方はろう学校でバドミントンを始めたのだそうです。話すうちにいろいろなエピソードが出てきます。出身地を聞けば「あの辺りだな」とイメージできますし、「あそこは寒冷地だから、きこえる子ども達も屋内競技のバドミントンに慣れ親しんでいる中で育ったんだな」と想像できたり。ろう学校までの通学の電車では周りの目が気になって補聴器は外していたとか、友達と手話で話していて、小さな子に珍しそうに見られていると思ったら母親がその子との間に割って入ってきてずっと冷たい目を向けられていたとか、とにかくいろんな話をしました。そうすると、だんだんと共通点が見つかるんです。わかる、自分もそうだった、覚えがある、わかる、と。この「わかる」というのを、まず自分が求めているのだと思います。そっくり同じ、あるいは多少違ってもほぼ似た思いをした、そこから関係性ができていくんですね。
――「わかるよ、自分もそうだったよ」と言われた時の学生の反応はいかがですか?
学生には「私も似たようなことがあった。今何とかなっているよ」と伝えています。言われた瞬間は首をひねっていますが、卒業してしばらくたってみれば「あの時言われたのはこういうことだったのかな」と感じてくれると思っています。
――大学教員のお仕事の2本柱である「教育」と「研究」のうち、「教育」の面で先生が大切にされていることは何ですか。
物事には本質があると知ること、あるいは表面だけ見るにしても、その見えているものをしっかりと語れることを学生には求めています。何かひとつのことに着目した時、そこから頭に浮かんだことを語れるかどうかですね。
――それを、授業を通して学生たちに伝えていると。
仮に日本語力が高い学生であれば、何かの概念を体系的に小論文くらいにまで仕上げられる力を見たいなと思いますし、手話は堪能なものの日本語には苦手意識がある学生であれば、ひとつのテーマから膨らませた論考を手話で端的に語れれば素晴らしいと思います。そういう、形としてアウトプットする以前の、日本語なら起承転結を構成できる力、手話であれば話題の提供から詳細を展開し 、空間活用という手話の利点を活かした語りができる力、そういうものを授業の中でも大切にしています。私の授業では課題や期末試験で 日本語による答案か、手話による答案の動画 を提出するいずれかを選べるものもあります。「自分史」の授業が正にそうですね。
――「自分史」の授業について、この授業が開設された経緯を教えて下さい。
過去に「聴覚障害教育研究」という、佐藤正幸先生(本学教授)と私の2人で担当する授業がありました。学生たちが障害者手帳交付、補聴器装用を皮切りにその後どのような教育を受けたのか、そういう教育制度の部分を佐藤先生が、親御さんや通っていた学校の先生に聞き取りをして学生が自分の過去を資料にまとめるという部分を私が担当していました。例えば、発音訓練を題材に、親御さんや先生にその頃の様子を聞いたり昔の写真や自分が描いた絵を集めるなどして、過去に受けた発音訓練を学生に再構成してもらいます。そうすると、それぞれの学生がどんな発音訓練を受けてきたのか、本当にいろいろな形が見えてきます。授業でのプレゼンを通してお互いにああだったこうだったと語り合うことができる。その中で、教育に関するキーワードや概念を佐藤先生が解説します。それによって、学生は聴覚障害教育の枠組みの中で自分や同級生がどの位置にいたのか、それぞれがどんなルートをたどって今に至っているのかを教育用語と結びつけながら理解します。そのありようは正に十人十色です。バックグラウンドが異なる学生たちが、新たに知る用語をそれぞれの経験と紐づけ、自分の中に落とし込んでいく。この授業の目的はそこでした。
その後、先ほどお話しした経緯があり、キャリア教育の文脈の中で聴覚障害教育に関する授業が別立てとなりました。そこで「自分史」が独立しています。
――「自分史」の授業について、詳しく教えて下さい。
この授業では、①生まれてからこれまでの自分史を作る②作成した自分史を、分析方法を決めて分析し、わかったことをまとめる③10年後の自分を想像してキャリアデザインを作る、という3つのことをします。
②は、就職活動の時に相手先に自分のことを説明するバックボーンになりますし、自分の中にブレない軸を持つためにも必要です。③は、その時どんな立場になっているか、結婚は?子どもは?というように、何でも良いので10年後の自分を自由に設定してもらいます。そうすると、そのゴールに到達するためにはどんなアクションが必要なのかが自ずと見えてくる。これをキャリアデザインとして発表してもらいます。もし時間が余れば、私が面接官役になって模擬面接をすることもあります。
――3つの課題に対して、学生からはどのような反応がありますか?
「10年後なんて想像できない!」とはよく言われます。「あ、そう?それだと就職活動もどうだろうね」と返しますが(笑)。毎年同じような反応ですね。
――なぜ学生たちは10年後を想像できないと言うのでしょうか。
まだ大学3年生ですからね、10年後がすぐにはピンと来ないのだと思います。
「こうなりたい」というのは、あくまで将来像であって具体的な年齢のイメージではないですよね。そうではなくもっと手前の区切りとして示すんですが、学生は初めおろおろします。
――「10年」という数字には、何か意味があるのでしょうか。
本当は12年後が良いんです。大学入学までの学校教育が12年間あって、そこまでは課題①の自分史でまとめている。それと同じ年数で次の12年とできれば良いのですが、計算がややこしいので、切りよく「自分史」の授業を受ける3年生の20歳からちょうど10年後の30歳としました。
――授業を受けた学生たちは、どんなコメントをしますか。
「役に立った」という声が多いです。就職活動に関する授業が3年生の2学期に設定されていて、以前は現学長の石原先生がご担当でした。その授業では就職活動に向けた自己分析の指導が入ります。これは一般的な意味での自己分析ですが、その前段として、きこえない自分を振り返るという作業が必要です。2学期の就職活動の授業は3年生全員が履修しますが、「自分史」の授業は半分くらいが取ります。授業課題である自分史も分析もキャリアデザインも、全て2学期の就職活動の授業に繋がります。
――「自分史」の授業を受ける学生たちには、どんな言葉をかけていらっしゃいますか?
「自分の道は自分で探せ、人生に責任を持って生きろ」と言っています。若い間はいくらでもやり直せる、私を見てみろと。20歳前でソ連に行くは、30前で米国に行くは 、40前で帰国してみるは、それでも今どうにかなっているだろうと。
――「大杉先生だからできるんだ」とはなりませんか?(笑)
何かしらのモチベーションにはなれているようですよ。ロールモデルほど立派なものではなく、「こんな人もいるんだな」ぐらいの(笑)。
――少し話が戻りますが、「自分史」の授業で、印象深かった出来事、エピソードはありますか?
(心理専門職ではない)素人の私が言うのもおこがましいですが、ろう・難聴者は、みな自分自身の聴覚障害とともに生きてきた、そこにはあまりにも多様な世界があります。そこに立ち入り、教え導いていくには、より高い技術と倫理が必要です。学生には、楽しかったことばかりを聞いていくわけではありません。苦しかったこと、葛藤したこと、やるせなかったこと、そんな様々な気持ちにも触れていくことになります。そこに向き合う時、彼ら自身が蓋をしていた感情が溢れてしまうこともあります。学生の気持ちが落ちてしまった時、自分はきちんと(教員としての)責任を果たせるのか。そういう意味では、「自分史」の授業をやるには相当な覚悟がいります。
授業ではまず、この授業で知りえたことを他言しない、プレゼンに対しては必ず質問をする、質問の時にはプレゼンで良かった点を挙げる、スライド作りが上手だったとかここをこうしたらもっと良くなるとか建設的なコメントをするということを学生と約束します。そうやって、丁寧に学生たちのそれまでの様々な経験を分かち合える場を作ります。中には、そうして場ができたことで、「ここでなら大丈夫だ」と、それまでの思いのたけをぶつける学生もいます。笑い話として披露する学生もいますし、泣きながら話す学生もいます。
以前、過去に家庭内で起きた衝突を一度は気にしないようにしていたけれど、この授業を機に思い切って家族とその時のことを話し合ってみたという学生がいました。話し合って初めてわかったことも多かったようです。そうして自分史を書き上げ、練習をしてさあ発表となった時、本人の中で感情が湧き上がったようで、堰を切ったように泣き始めたんです。文字通り号泣でしたが、その学生はプレゼンをやめませんでした。見ていた学生もみんなもらい泣きで、私もすぐにこれは涙腺がまずい、と思いました。きちんと受け止めようと発表を見続けたのですが、私の胸にも来るものがありました。
また、手話が分からず私とは筆談でコミュニケーションを取っていた学生がいました。その学生が「自分史」を受けたいと相談に来たんです。この授業で何をするかちゃんと分かっている、だからこそ受けたいと。それで受講してもらうことにして、その学生にも分かるように私の方でもスライド資料の文字を増やし、それを基に授業をするようにしました。ですがやはり(突発的なコメントも生じるので)それだけでは賄えません。どうしようかと思っていたら、周りの学生が「自分たちが何とかするよ」とその学生に声をかけたんです。彼らは、私が補足などを手話だけで話すと、それをタイピングして伝え始めました。
――パソコンノートテイクということですか?
まさしくそうです。それも、きこえない学生からきこえない学生へのパソコンノートテイクです。(註:一般的にパソコンノートテイクは、その場の音声をタイピングして文字で伝える。)
――本学ならではのシーンですね。先生も、支援を受ける学生も、支援をする学生も全員がきこえない人という。
その通りです。情報保障の原点ここにあり、自然発生的にそうなりました。私もそれに甘えるのではなく、自分にできる資料作りに努めましたが、どうしてもその場で思いついた話をしなければならない時は、支援に入ってくれている学生達とはアイコンタクトしながら授業を進めました。
――ノートテイクを受けていた学生は手話が分からなかったとのことですが、発表は手話だったのでしょうか。
そうですね、練習して、一生懸命発表していました。周りの学生もしっかり見届けました。少したどたどしさはあっても、その学生のスライド作りが上手なところも周りの学生には響いたようです。この授業は、情報系、工学系、デザイン系といろいろな学生が受けているので、スライドの作り方もそれぞれの色が出ています。
また別のケースでは、通学ができずずっとオンラインという学生から受講の希望がありました。そういった学生が例年1人2人はいます。その学生はオンライン受講、顔出し不可とのことで、周りの学生からもそのことへの理解が得られました。オンラインの学生からは教室にいる学生の顔がカメラを通じて見えますが、逆は見えない。彼らはそれでも良いと言ってくれました。その学生とは、授業とは別に週に1回時間を作り、オンラインで私に対してだけ発表してもらうようにしました。
――そうまでしても受講したい、という学生が毎年いるのですね。
そうですね、彼らは皆、通学できない自分も含めて自身と向き合いたい、この授業がそのラストチャンスととらえているように思います。
――そういった学生たちは、その後どんな風になりますか。
深い感謝をくれます。中には、わざわざ親御さんと一緒に飛行機で挨拶に来てくれた学生もいました。何かあったのかと思えば、「先生に会いに来ました」と言われて驚きました(笑)。
――その時、どんなお気持ちでしたか。
「ああ、役に立てたんだな」と。もうシンプルに、それだけですね。授業の時点でとても良い発表をしてくれている、そこですでに十分感動は味わっていますから。
――ここまでいろいろなお話を聞かせて下さった大杉先生が自分史をまとめるとしたら、どんな風になりそうですか。
本にすれば売れるかな(笑)。
自分が20歳だった時、10年後の目標はもう頭の中にありました。そこに到達するため歩んだという感じです。
――20歳の頃の10年後の目標というのは何だったのでしょうか。
今のロシア、昔のソ連から劇団を呼ぶことです。19歳で初めて訪れた外国が当時のソ連でした。渡航は容易ではありませんでしたが、「モスクワの劇団こそがろう者の演劇の最高峰、アメリカも目ではない」と聞いて、大学でロシア語を専攻する先輩と一緒に確かめに行ったんです。実際にこの目で見て、ボリショイバレエにもひけを取らないその質の高さに愕然としました。その体験が、例の10年間で国内のきこえない人たちの文化芸術を高めるのだというモチベーションになりました。世界最高峰の演劇を披露するために、普段の所作や食事のひとつひとつから役者は芝居を作っている、その様子を目の当たりにしたんです。その後、1991年に劇団を日本に呼ぶことができました。10年かかって実現しました。
――「自分史」の授業を担当する前と今とで、先生の中にどんな変化がありましたか?
学生がそれぞれ作る自分史の全てが、私にとっては宝物です。大学生でいられる時期は4年間、しかも私が彼らの授業を受け持つのはそのうち2年間だけです。そんな彼らのそれぞれの人生を、「自分史」を通して分かち合える。自分の子どものような年代の彼ら一人一人の人生に触れると「卒業しても頑張れ」と思いますし、数年後再会した時に(過去の自分史を引き合いに)「そういえば小さい時はこうこうだったね」と話せたりします。そういうつながりは、本当に宝物です。
私だけで独り占めするのはもったいないと思うのですが、(自分史は)個人情報なのでどう取り扱うかは今後の課題ですね。
――「自分史」の授業が、学生たちにとってどんな存在であって欲しいと思われますか。
「授業を休んだらもったいない」と思ってもらえたら。この授業は出席率がほぼ100%なんです。途中で履修をやめる学生もほとんどいません。これを、次に誰に引き継ぐかですね。
――在学生へのメッセージは過去のインタビューでいただいているので、最後に、全国のきこえない・きこえにくい小中学生、高校生にメッセージをお願いします。
「技大においで、ここには仲間がいるよ」。ろう・難聴者も一人では生きていけませんし、いつも力んで生きていたらいずれ疲れます。そんな時に大切なのは居場所です。私には居場所があちこちありすぎて考えものですが(笑)、居場所はつまりコミュニティと同義で、必要なものです。居場所は自分で作るもの。技大の仲間がその居場所になると思います。
――貴重なお話をどうもありがとうございました!
タイトル:筑波技術大学ウェブマガジン 大杉豊教授インタビュー