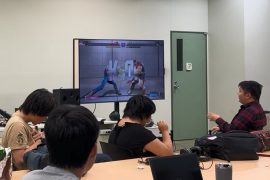2024年3月、筑波技術大学の学生4名が制作した映画『Eyeself~ワタシノセカイ~』が第2回彩の国市民映画祭でグランプリを受賞し、5月には中之島映画祭でも優秀賞を獲得しました。本作は、視覚に障害を持つ学生・八染まどかさんが自身の見え方を映像で表現した作品で、視野狭窄の世界を創造的かつリアルに描いています。制作にはプロの力も取り入れ、見え方の再現や撮影環境の調整に苦労しながらも、視覚障害への理解を広げることを目指して完成されました。本記事では、製作者である八染さんと山崎さんへのインタビューを通して、作品に込めた思いや制作の裏側を紹介します!
視覚障害と一口に言っても、その「見え方」は人それぞれ。

視野、視力、色覚の状態によって多様であり、まさに十人十色の世界が広がっています。それはまるで無限のグラデーションが織りなす光の絵のよう。だからこそ、自分がどのように世界を見ているのかを正確に他者に伝えるのは、非常に難しいことです。
そんな、個々に異なる「見え方」の世界を映像で表現した映画『Eyeself~ワタシノセカイ~』。本作がどのように誕生し、どのような思いが込められているのか、制作者である八染さんと山崎さんにお話を伺いました。
本作は、筑波技術大学情報システム学科の学生4人の「ロービジョンの世界を多くの人に伝えたい」という強い想いから制作されました。同作品は各地の映画祭で高く評価され、2024年3月の第2回彩の国市民映画祭でグランプリ(埼玉県知事表彰)を受賞し、同年5月には大阪の中之島映画祭で優秀賞も受賞しています。
あらすじ紹介
視覚に障害を持つ大学4年生の八染まどか。

彼女は、自身の視野狭窄という見え方を、持ち前の想像力を活かして楽しんでいた。 そんな彼女には、幼い頃からの夢があった・・・。 大学卒業を間近に控え、自身のお気に入りの場所を巡りながら、夢に挑戦するべくある場所へと向かいます。 彼女の夢とは一体、そして夢を叶えることはできるのか・・・。
インタビュー
Q1: 作品制作に至った経緯について教えてください。
八染さん:きっかけは授業でした。さまざまなアイデアが出る中で、私の「弱視の見え方」を映像作品として表現したいという考えが採用されました。最初は筑波の街紹介のような構想でしたが、制作を進めるうちに「見え方や感じ方」にフォーカスした作品へと変わっていきました。
また、もともとは料理動画の制作やまちづくりに関する映像企画を考えていましたが、最終的に「ロービジョンの世界を多くの人に伝えたい」という思いが強くなりました。4人の受講生で構成された制作チームで、当初は編集ソフトの操作練習なども行なっていました。しかし、より伝えたい世界を表現するために、プロの力を借りることを決めました。
Q2: 作品を作る中で難しかったことは何ですか?
山崎さん:撮影のための場所の使用許可を取るのが大変でした。マンションでの撮影許可や、警察による道路使用許可を自分たちで申請しなければならず、手続きが複雑でした。また、撮影用のドローンを飛ばす際にも許可が必要で、その準備にも苦労しました。

八染さん:一緒に撮影を行ったプロのスタッフは晴眼者だったため、私の見え方を伝えることが難しかったです。また、映像作品という特性上、細かな表情や動きをどのように表現するかが課題でした。視野狭窄の見え方を忠実に再現するために、外側がぼやけている様子を伝えるのも苦労しました。特に演技に関しては、表情の指導を受けることが多く、難しさを感じましたが、最終的には私の素直な反応、私自身の日常をありのまま表現すればいいと気づいて作品とすることができました。
Q3: 制作の中で最も印象に残っていることは何ですか?
八染さん:ジャイアントフラワーを作ってもらったことが印象に残っています。自分の中のイメージ通りに、大きな花の中に入り込んで撮影できたことはとても嬉しかったです。

山崎さん:特殊レンズを制作してもらったことです。映画の冒頭で花を見るシーンがあるのですが、そのシーンではプロの方の手作りの視野狭窄レンズを使用しました。レンズが完成した瞬間、作品に対するモチベーションが一気に高まりました。
Q4: この作品をどんな人に届けたいですか?
八染さん:視覚障害のない人に視野狭窄の見え方をイメージしてもらいたいです。視覚障害はネガティブに捉えられることが多いですが、その中でも楽しんで生きている人がいることを知ってほしいです。また、教育現場や研修などで教材として活用していただき、障害理解の一助となることを願っています。
山崎さん:障害の有無にかかわらず、多くの人に届いてほしいです。障害を単なる「困難」として捉えるのではなく、「楽しむ視点」があることを知ってもらえたら嬉しいです。
Q5: 在学中に映像制作プロジェクトを行ってみて感じたことはなんですか?
八染さん:映像制作はとても大変な作業でした。プロの方々はそれぞれのこだわりを持っており、それに対して私たちも「何を伝えたいのか」をしっかり持つことが大切だと感じました。映像表現は自由ですが、伝えたいことがあるならば、それにしっかり向き合い、形にすることで自分自身も納得できるのではないかと思います。
山崎さん:在学中でもやりたいことがあるなら、ぜひ挑戦してほしいです。周囲を巻き込むことで何かが形になることもあります。どんどん発信し、トライしていってほしいです。映像制作をする上では、「軸をぶらさないこと」が非常に大切だと感じました。